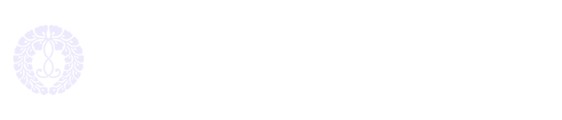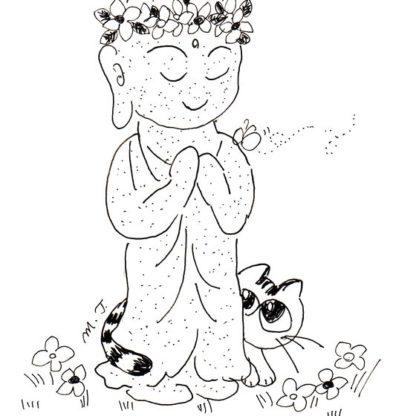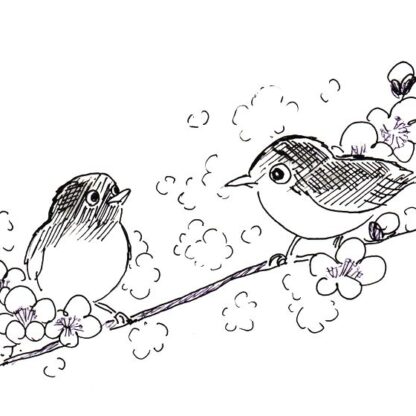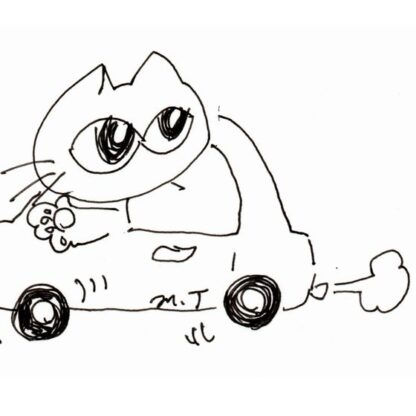あかねさす

 爽やかな風が吹く、初夏の吉野ヶ里遺跡を訪ねる事ができました。
爽やかな風が吹く、初夏の吉野ヶ里遺跡を訪ねる事ができました。
復元された弥生時代の集落の、物見櫓の柱には、12メートルの杉の木が柱として使われていて、何十人もの人が入れる最大の建物の主祭殿は、広い上に何階建て分にもなる高さの建物で、それらを作っていた技術にただただ驚くばかりでした。
そして、最高司祭者のプライベート空間は、室内を網代と衝立で仕切ったり、寝室は布の帳(とばり)で仕切られていました。日用品は植物で編まれた行李や土器が棚に置かれ、四つ脚の机や敷物もあり、今の私達の生活とあまり差がないように感じました。
入り口の階段に暫く座ってみましたら、風が心地よく吹き抜けていきます。そうなんです。高床式で作られているのです。司祭者はここから少し離れた主祭殿の最上階の部屋に移動して祀りをしていたのです。足腰が丈夫でないとならなかったろうなぁ、と思いました。
主祭殿の下の部屋(そもそも下の部屋が2階以上の高さです)ではクニのまつりごとが行われていました。集落だけでなく、クニ全体にとって最も重要な場所であったのでしょう。田植えや稲刈りの日取りや季節ごとのお祭りの日を決めたり、大きな「市」を開く日取りを決めるなど、クニ全体の重要な物事についての話し合いと祖先への祀りが行われていた場所と考えられています。話し合いで決まらない時には、神や祖先の声が聞ける最高司祭者に決定を委ねたのでしょう。
高床式と言えば正倉院ですが、その千年も前から高床式の技術があった事に大変驚きました。
そして、弥生時代に絹織物があった事や、織物を茜(赤根)や貝紫で染めていた事に更に驚きました。
以前、代々の皇后様がお育てになっている蚕の糸が、正倉院織物の古代裂修復に適していると何かで読んだ事があります。一般的な蚕ではなく、皇室で育てている日本古来からの蚕の小さな繭の細い糸でないと修復に適さないのだそうです。
私の中で、弥生時代から奈良時代が、お蚕さまの細い糸で繋がりました。お蚕さまの生命の糸を無駄にしない工夫もきっとその頃からあったに違いありません。
そして高床式の建物から見える登る朝陽は『あかねさす』色であったでしょうね。