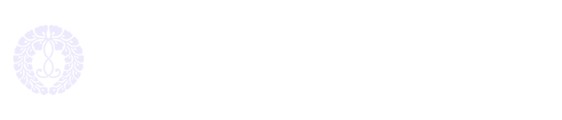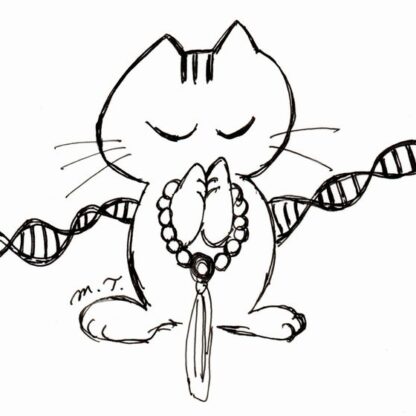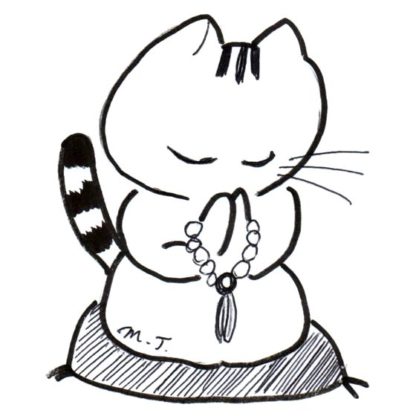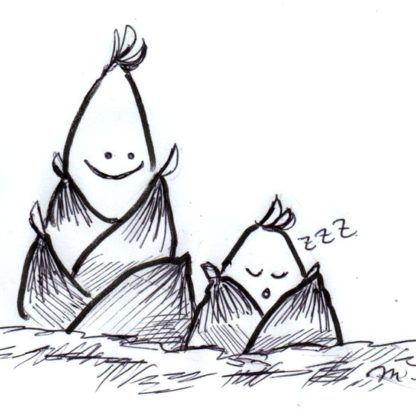ショーケンとは

 「ショーケン?」と言いながら首を傾げられてしまいました。ショーケンがわからないのです(俳優だった萩原健一さんではありません)。朝晩と秋らしくなり、さすがにもう夏の着物は着ないであろう、と、持ち込んだクリーニングやさんで着物の正絹がわからなかったのです。
「ショーケン?」と言いながら首を傾げられてしまいました。ショーケンがわからないのです(俳優だった萩原健一さんではありません)。朝晩と秋らしくなり、さすがにもう夏の着物は着ないであろう、と、持ち込んだクリーニングやさんで着物の正絹がわからなかったのです。
着物に詳しい店員さんがいる曜日に持ち込みましたが、シフトが変わってしまったようでした。絽、紗、紋紗、麻等生地をお伝えしてクリーニングをお願いしました。今は着物を着る人が少ないですから仕方ありません。
少し前に着物警察という言葉を知りました。着物を正しく着ていない人を注意する人の事なんだそうです。私など、かなりいい加減な着方をしてますから、ひゃー、怖い!となります。
まして、このところの温暖化で、体感に合わせて着物を着ていますから、本来なら裏地がある袷の時期でも、半袖の気候なら単衣にしてますし、透ける夏着物も以前より長い期間着ています。思えば母は普段着が着物の人でしたので、袷が暑い時には、裾は袷でも背中は単衣の胴抜き仕立てやいろいろな工夫をしていました。
さて、法衣の衣替えについても、何年か前から気候に合わせてでよいとお達しがありましたので、正直ホッとしています。以前は5月10月に透ける法衣というのにとても抵抗がありましたが、洋服なら半袖を着ている日もあります。夏物の透ける素材の法衣は軽やかで涼やかで見ている側も涼しく感じます。暑い時に相手に涼を感じてもらうというのも、布施行の一つかもしれません。
そういえば女性の夏着物や夏帯の柄は、流水の他は秋の草花が多いのです。盛夏に秋の柄は季節先取りの粋と共に、涼やかな秋に想いを馳せる古人の知恵ですね。夜、虫の声を耳にして、母の夏帯の萩と鈴虫柄を思い出しました。
萩と言えば、童謡「しょじょじのたぬきばやし」の2番は、「しょじょじの萩は月夜に花盛り」と歌います。
野口雨情さんたら、1番の歌詞の「和尚さん」は浄土真宗やおまへん、と思いますが、2番は流石ですよ。以前お参りしました時、證城寺さまの萩は白萩でしたから、きっと秋の月夜に映える事と思います。