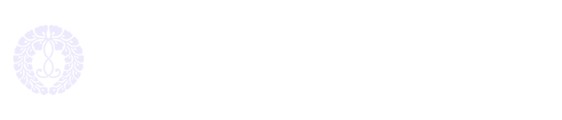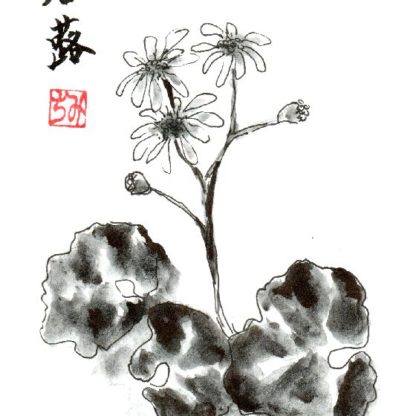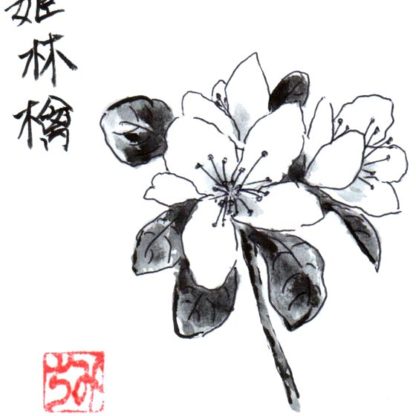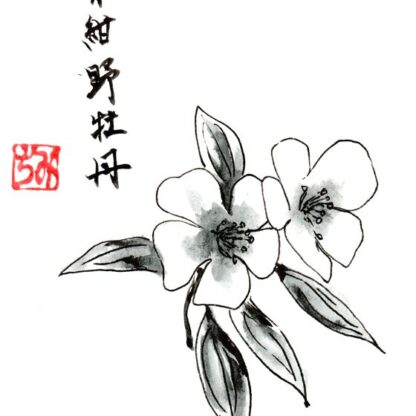仏法の鏡の前に

 こどもの頃に聞いた地獄の鏡のことが忘れられません。本当か嘘かを調べられて、嘘だったら舌を抜かれる、ということに「舌は強く引っ張ると抜けるんだ」という恐怖心に震えました。
こどもの頃に聞いた地獄の鏡のことが忘れられません。本当か嘘かを調べられて、嘘だったら舌を抜かれる、ということに「舌は強く引っ張ると抜けるんだ」という恐怖心に震えました。
これは浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)のことで、閻魔大王が人を裁くとき、善悪の見きわめに使用する地獄に存在するとされる鏡のことです。
この鏡にはその人の生前の一挙手一投足が映し出されるため、どんな隠し事も出来ません。生前に犯した罪の様子がはっきりと映し出されて、これで嘘をついていることが判明した場合には、舌を抜かれてしまうというのです。そして、ここで映し出されるのはその人の人生だけでなく、その人生が他人にどんな影響を及ぼしたか、またその者のことを他人がどんな風に考えていたか、といったことまでがわかるということです。舌を抜かれるとともに恐ろしいことです。
しかし、この鏡は人を罰するためではなく、自らの罪を見せることで反省を促すためのものともいわれています。
このような鏡の前に引き出されたら、どのような人も深く頭を下げる以外に何も出来ないでしょう。
親鸞聖人は『正像末和讃』に
外儀のすがたはひとごとに
賢善精進現ぜしむ
貧瞋邪偽おおきゆえ
奸詐ももはしみにみてり
(人は誰でも外向きの姿は賢こぶり善人ぶって精進らしく見せているが内心は貪り・怒り・偽りに満ちていて人を欺きだましてばかりいる)
日頃、隠されている私の本当の姿を表されています。
「経教(きょうきょう)はこれを喩ふるに鏡(きょう)のごとし。しばしば読みしばしば尋ぬれば、智慧を開発す」
中国の善導大師の著書『観経疏』の中にある言葉で「お経に説かれた仏さまの教え(仏法)は、鏡のようなものです。何度も読み、何度もその心を訊ねるならば、智慧を生み出します」とお示しくださっています。
仏法を聴聞することは知識や教養を高めるためではなく、「私」の本質をしっかりを写し出す鏡の前に身を置くことだったのです。
毎日、仏法の鏡の前に向かいましょう。